•Nature
NatureではSARS-CoV-2の長期の免疫記憶について2つの論文が掲載されており,NEWS AND VIEWSにも取り挙げられている。
1)COVID-19
SARS-CoV-2感染は長期生存する骨髄形質細胞を誘導する(SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans) |
米国St.Louisにあるワシントン大学からの報告である。抗原消失後に骨髄中の抗原特異的な形質細胞が長期維持されることは一般に知られてきた現象だが,COVID-19感染後の患者を発症時から約1年かけてフォローして血液を縦断的に調べた内容である。
Fig.1Aに示されているとおり特に18名については7カ月後に骨髄血まで採取して,COVID-19に感染せずワクチンも接種していなかった11名の健常者と比較している。論文全体としては観察研究にとどまっており,話題性が重視されたものと思われる。
1年かけてSARS-CoV-2に対する抗体価は下がっていくものの,約7カ月後の骨髄中の形質細胞を磁気ビーズで単離してSARS-CoV-2のS蛋白質に特異的な抗体を産生する細胞を定量したところ,ばらつきはあるが,0.1%の割合でS蛋白質に反応する形質細胞が認められ,細胞増殖の指標となるki67は陰性だったことから静止期の細胞と考えられた(
Fig.3)。研究者たちはS蛋白質に特異的なメモリーB細胞が末梢血に少なくとも7カ月間は維持されることも示している(
Fig.4)。
SARS-CoV-2感染1年後には他変異株への抗体中和能も自然に強化された(Naturally enhanced neutralizing breadth against SARS-CoV-2 one year after infection) |
ロックフェラー大学を中心とする共同研究の報告である。COVID-19感染後の26歳から73歳までの患者63名について,もともと感染後1.3カ月と6.2カ月のところで免疫応答を調べていたが,2021年3月に1年後のフォローが行われた。そのうち26名はmRNAワクチンを少なくとも1回は接種していた。SARS-CoV-2の抗体測定は中和活性と相関することが知られているS蛋白質の受容体結合部位(RBD)に対する抗体に着目した。ワクチンを受けていない患者では12カ月かけて抗体価が低下したが,ワクチンを接種すると30倍に上昇した(
Fig.1)。中和活性についてはシュードウイルス(HIV-1にSARS-CoV-2のS蛋白質を発現させたもの)を用いて実施されたが,ワクチン接種後50倍に上昇することを確認した。変異株であるB.1.1.7(Alpha),B.1.351(Beta),B.1.526(Iota),P.1(Gamma)株(変異株の名称は偏見を避けるために名称が変更されているので注意されたい:
リンク)に対する中和活性をワクチン接種群と非接種群で比較したところ,ワクチン接種群では「野生型」SARS-CoV-2(以前,武漢型と呼ばれていた型)に対する中和活性が感染後だけでなくワクチン接種後と比べてもさらに高い中和活性を示しているという驚きの結果だった。
何が起きているのか調べるためにまずはRBDに特異的なメモリーB細胞を数えたところ,COVID-19罹患して1年後も,6カ月後よりも数は減ったもののRBD特異的メモリーB細胞は少数存在することと,ワクチン接種後には著しく増えることを確認した(
Fig.2)。研究者らはCOVID-19罹患後1~6カ月後にかけてメモリーB細胞が体細胞超変異(
somatic hypermutation)を起こしRBD変異に対しても抗体結合能を失いにくいように「進化」することを1月に報告している(
リンク)が,今回はCOVID-19罹患後6~12カ月の間にも進化したのか,6カ月後と12カ月後をペアで比較できるように10名の患者(うち6名はワクチン接種後)から1105ペアのモノクローナル抗体を作成し抗体の重鎖と軽鎖をコードするDNA塩基配列を調べ,RBD特異的メモリーB細胞の進化は続いていると述べている。特にワクチン接種患者では6名ともB細胞クローンの増殖を認めた。体細胞超変異についてはワクチン接種を受けていてもいなくても6~12カ月にかけて続いていることがわかった。研究者たちはワクチン接種後にメモリーB細胞が体細胞超変異を加速させるわけでないと結論づけた。
この後はワクチン接種の有無は関係なく研究を進めている。研究者たちはCOVID-19罹患後6カ月後と12カ月後では,抗体のRBDへの結合力と中和能が高まることを示した後,抗体の中和能が変異株にも及ぶメカニズムについても調べた。COVID-19罹患後1カ月後と12カ月後,中和能のある抗体と中和能を持たない抗体が同数になるようにランダムに60クローンのモノクローナル抗体を選んだ。Biolayer interferometry(BLI)という装置を用いて,対象の抗体がRBDに結合することによりRBDが構造変化を起こして他の抗体の結合を阻害しないか調べる検討を行った。中和能を持たない抗体30クローンのうち2クローンではRBDの代表的なエピトープ(
リンク)であるclass 1(C105),class 2(C121,C144),class 3(C135)のいずれかへの抗体結合を阻害することがわかった。その一方で中和能を持つ抗体では30クローンのうち28クローンでACE2と結合する部位のRBDエピトープを認識するclass 1あるいはclass 2の抗体の結合を阻害した(
Fig.4c)。また,抗体がRBDに結合することによってもう一つの抗体がclass 1とclass2に結合するのが阻害されるかを調べたところ,COVID-19罹患後1カ月後の血液から作製されたモノクローナル抗体では15クローン中9クローンでclass 1とclass2抗体の結合がいずれも阻害されたが,12カ月後では15クローン中1クローンだけでしか阻害されなかった。すなわち,ACE2との結合を阻害しないRBD抗体は,抗体レパートリーから排除されることを見出した。最後に1カ月後と12カ月後のそれぞれから作製された中和能を持つ抗体をランダムに15ペア選択して変異株への反応を比較したところ,15ペアとも変異株への中和能を獲得したことがわかった。
今回はCOVID-19罹患後の患者を対象にした研究だったが,研究者たちは罹患したことがない健常者についても言及し,ワクチン接種を受けていれば同様のことが言える可能性があり,適切な時期に追加接種を受けることで変異株への有効性も高まるのではないかと述べている。また,日本でも最近承認された抗体カクテル療法はimdevimabとcasirivimabの合剤だが,お互いに競合することなくRBDの異なるエピトープに結合する抗体してSARS-CoV-2のACE2との結合を阻害できることを利用しており,抗体レパートリーの進化後を模倣した治療ともいえそうだ。
•Science
1)COVID-19
老化細胞除去はコロナウイルス感染によるマウスの致死を回避する(Senolytics reduce coronavirus-related mortality in old mice) |
近年様々な疾患において老化細胞除去(Senolysis)が治療戦略となる可能性が期待されている。呼吸器においてもCOPDや肺線維症などでその可能性を示した本邦からの報告があり,昨年はNature誌にCAR-T療法まで検討されていることが報告されTJHでも紹介された(
No.103)。メカニズムの研究も進められ細胞内グルタミン代謝阻害が老化細胞の除去につながることが本邦からScience誌に報告されTJHでも本年1月に紹介された(
No.129)。
細胞老化は細胞ストレスによって引き起こされる現象で外因性でも内因性でも起こりえる現象である。老化した細胞が放出する炎症性サイトカインやプロテアーゼなどの様々な生理活性物質について総称したものがSenescence-associate secretory phenotype(SASP)(
リンク)である。本来SASPは老化した細胞やその周辺細胞を免疫細胞によって除去する役割をもち,癌抑制に効いている。その一方で加齢や慢性炎症で老化細胞が蓄積してくると免疫システムにも干渉して,老化細胞の除去がうまく行かなくなり,過剰な炎症性サイトカインの産生などの引き金になり悪循環に陥る。この現象は免疫細胞を含めて様々な臓器細胞に起こりえるもので,無菌状態での慢性炎症を引き起こし,線維化などの病態をもたらすと考えられている。
今回の論文は米国ミネソタ大学と同じ州のメイヨークリニックの研究チームからの報告で,研究者らは老化細胞やSASPによって引き起こされる現象が,COVID-19のサイトカインストームによって起きる病態と関連し,特に高齢者で重症化しやすいことを説明できるのではないかと考えて,新薬候補である
fisetinの非臨床試験まで示している。
まずは単純な実験から始まっている。放射線を照射して細胞老化を誘発したヒト脂肪前駆細胞を用意し,病原体に共通した構造体(pathogen-associated molecular patterns:PAMPs)としてよく用いられるリポポリサッカライド(LPS)を加えて放射線を照射していない細胞と比較したところ,SASPの分泌は老化細胞の方が強く上昇した。次にin vivoの実験でも,若齢と老齢マウスにLPS刺激を与えて24時間後のSASPの分泌を調べたところ,肝臓や腎臓での一連のSASPは老齢マウスのほうで特に大きく上昇していた(
Fig.1)。早老症の疾患モデルマウスも用いて同様の結果が得られることも確認し,老化細胞が病原体に暴露するとサイトカインストームが起きやすいと結論付けた。
次にSARS-CoV-2が老化細胞に与える影響を調べるため,老化したヒト腎臓血管内皮細胞や皮下脂肪前駆細胞に組換えS蛋白質を添加したところ,SASPの分泌が上昇することを示した(
Fig.2)。さらにSASPそのものが与える影響を調べるため,老化していない初代腎臓血管内皮細胞を老化細胞または非老化細胞の培養に使用した培地(条件培地)に晒したところ老化細胞の条件培地に晒された方ではウイルス防御因子として知られるIFITM2やIFITM3といった遺伝子発現が優位に低下することがわかった。IL-6/IL-8といったサイトカインの上流に位置するIL-1αに着目して,同じ細胞にかけてみるとやはり,IFITM2やIFITM3は低下し,条件培地にIL-18,PAI-1,IL-1αの中和抗体を添加しておくとIFITM2やIFITM3の抑制効果は弱いものになった。このことから老化細胞によるSASPの分泌が老化していないヒト血管内皮細胞にも悪影響を及ぼすと考えた。
次に老化していないヒト初代呼吸器上皮細胞を用いて,老化したヒト脂肪前駆細胞や腎臓血管内皮細胞や臍帯血管内皮細胞(HUVEC細胞)の条件培地に晒すと,ACE2やTMPRSS2の発現が亢進することも見出し,IL-1αを添加するだけでも同様の現象を確認した。さらに5例の高齢者患者の手術を受ける時に採取された健常な肺組織の部分を用いてTMPRSS2と細胞老化マーカーであるp16INK4aを免疫染色したところ,それぞれの陽性細胞が隣接していることがわかった。以上より,老化細胞がSASPを介してサイトカインストームを引き起こしうること,隣接する非老化細胞をSARS-CoV-2に感染しやすくすることがわかった。
研究者たちはコロナウイルスのin vivo研究に向かうがここで紹介されているNormal Microbial Experience(NME)というモデルは,この研究グループの独自モデルのようで既報が引用されていて興味深い。通常,研究のためにマウスを維持するときは特定の病原体を排除した環境(SPF)の下で飼うことが多いが,このNMEモデルはSPFで飼った老齢マウス(20月齢以上)を一般の汚染された環境で飼われていたマウスと一緒に飼うと2週間も経たないうちに死んでしまうというモデルである。対照的に若齢マウスでは何カ月も一緒に飼ってもあまり死なないので,加齢が個体死に影響することがわかる(
Fig.3)。NME曝露後,6〜7日目にマウスを調べてみると肝臓,腎臓,程度は少ないが肺において細胞老化マーカーであるp21Cip1やp16Ink4a,SASPが老齢マウスにおいて多く検出された。NMEマウスの病原体について唾液や糞便を調べたところ,SARS-CoV-2と同じβコロナウイルス系統に属するマウス肝炎ウイルス(MHV)など複数のウイルスが含まれており,老齢マウスの血液を調べたところ,MHVだけが陽性になったことや,その肝臓を調べたところMHV陽性の壊死性肝炎や特徴的な合胞体形成を認めた。小腸大腸にも感染像を認めた。若齢マウスではこのような所見は認めなかったことから,NMEマウスの病原性はMHVにあると考えられた。さらに証明するため,老齢マウスに対して,致死量に満たないMHV株をあらかじめ感染させることで免疫してみたところ,若齢マウスよりは免疫応答が弱かったものの,その後のNME曝露後でほとんど死ななくなったことから,NME曝露によって老齢マウスが死ぬ原因はMHVにあることを証明した。
研究者らは老化細胞にアポトーシスを誘導する薬剤として報告されていたフラボノールの一種であるfisetinを試した(
Fig.4)。老齢マウスをNMEに1週間曝露し,曝露開始後3〜5,10〜12,17〜19日目に20mg/kgのfisetinを強制的に経口投与し,それ以外の期間は餌に500ppm含ませることで維持量とした。有害事象は認めなかった。結果,雄マウスは64%,雌マウスは22%長期生存することができた。MHVウイルスに対する抗体を調べたところ,fisetinを投与したマウスでは抗体価も若齢マウス並みに上昇していた。さらに細胞老化マーカーやSASPを調べたところ,fisetinを投与してNMEに曝露したマウスではいずれも低下していた。
以上より加齢により免疫反応が低下していたのは老化細胞が原因で,fisetin投与により細胞老化やSASPや炎症が抑制され,老齢マウスの生存やウイルスへの抗体反応の改善につながったと解釈した。
さらにfisetinの作用機序を明らかにするため,2種類の実験を追加している(
Fig.5)。1つ目は遺伝子工学的に開発されたINK-ATTACマウスを用いて,薬剤(AP20187)の投与によりp16INK4aを発現する老化細胞を選択的にアポトーシス誘導して除去できる仕組みを利用した。老齢マウス(>24月齢)に対して薬剤で老化細胞を除去しながらNME曝露を行ったところ,雄雌マウスともに致死が遅れ,MHVウイルス量も減少することを確認した,2つ目はすでによく知られている老化細胞除去薬であるDasatinibとQuescetinの配合剤(D+Q)を投与する実験を行った。NME曝露後2回に分けて投与したところ,50%のマウスが生き延びた。最後にfisetinの予防的効果を調べるため,NME曝露の3日前に2日間のfisetin(20mg/kg/日)投与をして,NME曝露後は少量投与としたところ雄雌マウスともに致死率は40%だった。短期間のfisetin投与(少量投与は行わない)場合についても検討し,NME曝露後3,4日目の2回投与の場合,3,4日目および10,11日目の4回投与の場合ではそれぞれ致死を遅らせる効果を認めた。研究者らはfisetin半減期は5時間と短いことを考えると作用機序は「hit and run」様式で,fisetinは持続的に何かを標的としているのではなく,老化細胞除去に効いており,ウイルス感染の前後で致死を避けるためにパルス的に投与するのが良いだろうとしている。
研究者たちは老化細胞があることで病原体に曝露したときのSASPの分泌応答が増大することをAmplifier(/Rheostat)仮説(
Fig.5)として説明しており,今回の知見をもとにすでにCOVID-19患者を対象にfisetin投与の臨床治験を開始したことも述べている。
•NEJM
1)癌
ステロイド抵抗性慢性GVDHに対するRuxolitinibの有効性(第三相臨床治験)(Ruxolitinib for glucocorticoid-refractory chronic graft-versus-host disease) |
日本では骨髄線維症や真性多血症の治療薬として承認されているJAK1-JAK2阻害薬である
ルキソリチニブの慢性GVHDに対する有効性を調べた第三相臨床治験の報告である。急性GVHDの第三相臨床治験結果については2020年にNEJMに有効性が報告されており(
リンク)今後の日本での承認が待たれるところである。JAK阻害薬はJAK1,JAK2,JAK3の阻害の仕方が薬剤によって異なることや,開発経緯から適応症も違うため注意が必要だが,もう1つのJAK1-JAK2阻害薬には
バリシチニブがあり,そちらは重症のCOVID-19肺炎に承認されたのは記憶に新しい。
慢性移植片対宿主病(GVHD)は同種造血幹細胞移植の主要な合併症で,ステロイド抵抗性あるいはステロイド依存性の患者が50%を占める。しかしながら,セカンドラインとしての治療手段として第三相臨床治験によって裏付けられたものはこれまでなかったと述べられている。今回の治験はNovartis社とIncyte社がスポンサーとなって実施され,ステロイド抵抗性急性GVHDを対照とした第二相治験(REACH1),その第三相治験(REACH2)に続く3番目の治験(REACH3)である。内容は中等度または重度のステロイド抵抗性もしくは依存性の慢性GVHDを有する12歳以上の患者を対象に実施された第3相非盲検ランダム化比較試験である。ルキソリチニブ10mgを1日2回投与し,その有効性と安全性を調べた。比較対照は従来の最善とされる治療法で広く行われている10種類の治療法から治験担当医師が選択する形で,具体的には34.8%は体外循環光療法が実施され,22.2%はミコフェノール酸モフェチル,17.1%はイブルチニブ(日本では慢性GVHDに対して未承認だが申請中とのこと),約半数はカルシニューリン阻害薬が処方された。
主要評価項目は,24週時点での全体的な奏効(完全または部分的な奏効)で,副次評価項目は,治療が奏功している生存期間と,24週時点での修正Lee症状尺度スコア(慢性GVHDの症状をスコア化したもの)の改善度合いとされた。
2017年7月11日から2019年11月18日にかけて,329例が無作為化され,165例がルキソリチニブの投与を受ける群,164例が対照治療を受ける群に割り付けられ,28か国149病院(日本からも16病院が参加)で実施された。2020年5月8日でデータ収集が終了し(観察期間中央値は57.3週),その時点で125例(38%)がランダム化治療を継続できており,82例がルキソリチニブを中断,122例が対照治療を中断となっていた。治療中止の理由として「効果がない」(ルキソチニブ14.5%に対して対照治療では42.7%),有害事象(17.0%に対して4.9%),基礎疾患の再発(5.5%に対して4.3%)だった。61例は対照治療からルキソリチニブにクロスオーバーされた。
治験結果について有効性はルキソリチニブ群に軍配が上がった(
Figure 2),24週時点での全体的な奏効割合はルキソリチニブ群のほうが対照治療群よりも有意に高く(49.7%に対して25.6%,オッズ比2.99),治療が奏功している生存期間の中央値も有意に長かった(>18.6カ月に対して5.7カ月,ハザード比0.37),症状も改善を認める割合が高かった(24.2%に対して11.0%,オッズ比2.62)。
24週目までに発現した有害事象として重篤なものはルキソチニブ群で33.3%,対照治療群で36.7%と,慢性GVHDの治療がそもそも難しいことが反映されていると思われる。ただし,グレード3以上については,血小板減少(15.2%に対して10.1%),貧血(12.7%に対して7.6%)がルキソチニブ群で目立っていた。肺炎は8.5%に対して9.5%と大きな差はなく,感染症全般についても19.4%に対して18.4%だったが,真菌感染は11.5%に対して5.7%とルキソチニブ群が少し多く,感染症予防薬が必要になる可能性も述べられている。サイトメガロウイルス感染は5.5%に対して8.2%だった。11例が治験薬に関連して死亡しており,ルキソチニブ群で7例,対照治療群で4例だった。
呼吸器専門医にとって慢性GVHDで特に問題となるのは閉塞性細気管支炎で,Discussionにも述べられているが,残念ながら肺と肝臓における治療反応性はルキソチニブ群も対照治療群のいずれでも乏しかったと述べられており,これについては今後のさらなる治療薬開発を期待したい。
最後になったがご紹介いただいたので,7月7日号に掲載された私たちの研究室から報告したScience Translational Medicineについても少しだけ紹介しておきたい。すでに
プレスリリースしており,幸いにして表紙にも取り挙げていただいたのでここでは簡単に触れさせていただく。
•Science Translational Medicine
1)iPS細胞
iPS細胞とマイクロ流体気道チップ技術を組み合わせた多細胞での線毛病モデルの構築(Multicellular modeling of ciliopathy by combining iPS cells and microfluidic airway-on-a-chip technology)
|
ヒトiPS細胞から分化誘導した気道上皮細胞に対して工学的に設計された「臓器チップ(organ-on-a-chip)」を用いて液流による物理刺激を加えながら培養することによりin vitroでは実現困難だった細胞間の線毛協調運動を実現して,原発性線毛機能不全症候群の病態解析にも役立てた。
私たちはヒトiPS細胞を呼吸器分野での疾患モデルや再生医療に役立てるべく,様々なアプローチを行ってきたが,一連の取り組みの1つは,iPS細胞の有用性を呼吸器の分野でなるべくわかりやすい形で明らかにすることである。私たちは気道上皮細胞の分化誘導法を確立(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26724905/)したが,この頃から臨床現場で診断から治療まで多くの困難を抱えてきた原発性線毛機能不全症候群(Primary Ciliary Dyskinesia:PCD)に着目してきた。この疾患については複十字病院の森本耕三先生や慶長直人先生らによる大変わかりやすい総説が呼吸臨床2020年6月に掲載されているので是非参照されたい(
リンク)。
PCDの診断は遺伝子検査,電子顕微鏡,鼻腔NO,免疫染色,高速ビデオカメラなど,様々なモダリティを駆使するため,複数の診療科が協力して実施することが多い。呼吸器内科だけでなく,耳鼻咽喉科・小児科・呼吸器外科が協力して臨床に取り組み,今回の研究においてもその協力体制が発揮できたのは幸運だったと言える。今回の論文内容だけにとどまらず,多くの機関から患者さんにご協力いただいており,患者さんとご家族の皆様と主治医の先生方に心より感謝したい。
PCDや鑑別を要する難治性の気管支拡張症には未知の遺伝子変異や線毛関連の機能異常がまだ多く存在すると考えられている。今回の論文では,気道上皮細胞の線毛協調運動を「臓器チップ」を用いて生体内に近い形に再現することができただけでなく,末梢血から樹立可能なiPS細胞を気道上皮細胞に分化誘導して線毛運動の様々な異常パターンをin vitroで再現することもできた。さらに既報のない遺伝子変異でも候補があればゲノム編集によって因果関係を同じ変異を持つ患者さんが1人だったとしても証明できること,従来の細胞培養では難しかった「臓器チップ」を用いた高度な疾患モデルを実現できることを示した。
今までPCD疑いのままで確定診断がペンディングされたような様々な診断困難症例は多く存在する。現在はまだ研究段階ではあるが,将来はiPS細胞を利用することでこういった診断困難症例の病態理解が一層進むことを期待したい。さらには診断だけでなく,初代細胞と違って恒久的に増やせる長所を持つiPS細胞なら多くの気道上皮細胞を繰り返し分化誘導できるので,治療薬の開発にも役立つのではないかと考えている。
今週の写真:京都の八瀬近くの森の中を散策しました。 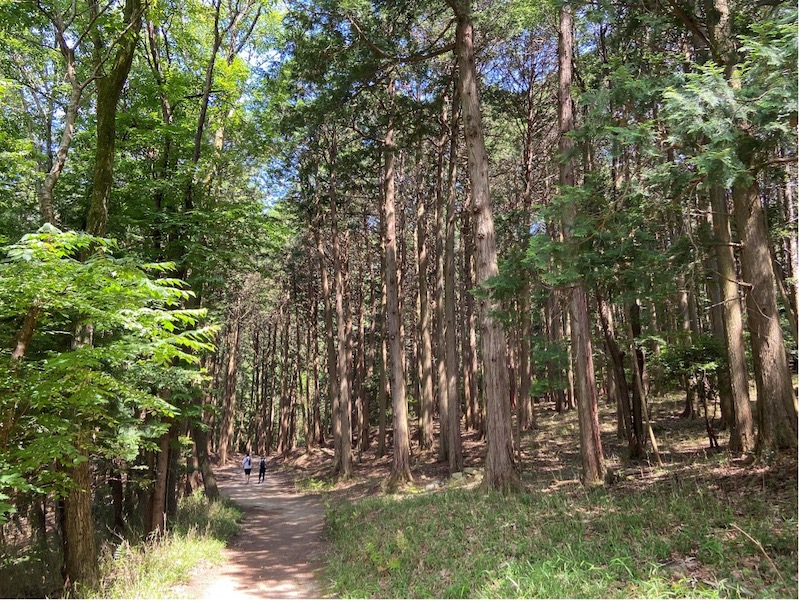
|
(後藤慎平)